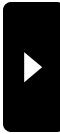2017年11月26日
【No.1524】伝統を残すために未来を犠牲にしてはいけない
あらためて沖縄の染織について、歴史を整理しながら振り返ってみると面白い。
15世紀から19世紀後半まで、琉球王国として独立した国家だった。この約450年の間、中国(明・清)を中心に、日本、東アジアとの交易を通じて、各国から多種多様な技法を吸収して王朝文化のもとで発展してきました。

伝統、革新、伝統、革新・・・この言葉がここ最近ずっと頭をグルグル巡っています。こうやって沖縄染織の歴史を見てみると、例えば、1611年木綿の種子を取り入れる、1619年久米島に養蚕が伝わる、1690年絣の記録がはじめて登場などなど、素材や技術など革新が結構あったんだなと感じます。
そんな中、近年の転換点が1970年代後半から80年代後半に出てくる重要無形文化財指定や、伝統的工芸品の指定だったのではないでしょうか。その後の流れを見ても、この時期から業界として「伝統を守る」という流れが加速していきます。
もちろん文化財や伝産指定された事はすばらしい事だし、伝統を継承する事はとても重要だと思います。
特に沖縄戦の後、焦土の中から工芸を復活させ、それを継承されてきた方々に対して敬意を払わねばなりません。

ただ僕が1つだけ懸念しているのが、この30年くらい「伝統を守る」事にウェイトを置きすぎているのではないかという事です。それによって、現在の作り手の低収入、後継者不足、原材料不足といった大きな課題が長い間ずっと解決されていないのではないでしょうか。
世代交代がもう始まっていて、残された時間はありません。特に現状の課題について、これまでの呉服業界の流通構造が大きな原因になっている事は明らかです。なぜこんなに技術も持ち、すばらしい仕事をされている作り手の多くが月収10万円以下(5万円以下の方も普通にいます)、時給換算すると200円とか300円という状況なのでしょうか。これでは、売れれば売れるほど苦しくなります。
作り手の皆さんとお話しすると、作るのが本当に好きで、「染めたり織ったりしている時が本当に楽しい」という言葉を良く聞きます。
僕はだからこそ、作る人達がもっと収入の事を考えなければいけないと思います。そして、適正な収入があり、安心してモノづくりができる仕組みを多種多様な人々が集まって構築する必要があると思います。
もう待ったなしで伝統や思いなど守るべきコトを業界として再確認した上で、変革の具体的アクションを起こす時です。
今のままだと、伝統を守るために未来が犠牲になっていると言っても過言ではありません。残すべき伝統を未来に繋ぎ、次の発展のための「変革」です。
15世紀から19世紀後半まで、琉球王国として独立した国家だった。この約450年の間、中国(明・清)を中心に、日本、東アジアとの交易を通じて、各国から多種多様な技法を吸収して王朝文化のもとで発展してきました。

伝統、革新、伝統、革新・・・この言葉がここ最近ずっと頭をグルグル巡っています。こうやって沖縄染織の歴史を見てみると、例えば、1611年木綿の種子を取り入れる、1619年久米島に養蚕が伝わる、1690年絣の記録がはじめて登場などなど、素材や技術など革新が結構あったんだなと感じます。
そんな中、近年の転換点が1970年代後半から80年代後半に出てくる重要無形文化財指定や、伝統的工芸品の指定だったのではないでしょうか。その後の流れを見ても、この時期から業界として「伝統を守る」という流れが加速していきます。
もちろん文化財や伝産指定された事はすばらしい事だし、伝統を継承する事はとても重要だと思います。
特に沖縄戦の後、焦土の中から工芸を復活させ、それを継承されてきた方々に対して敬意を払わねばなりません。

ただ僕が1つだけ懸念しているのが、この30年くらい「伝統を守る」事にウェイトを置きすぎているのではないかという事です。それによって、現在の作り手の低収入、後継者不足、原材料不足といった大きな課題が長い間ずっと解決されていないのではないでしょうか。
世代交代がもう始まっていて、残された時間はありません。特に現状の課題について、これまでの呉服業界の流通構造が大きな原因になっている事は明らかです。なぜこんなに技術も持ち、すばらしい仕事をされている作り手の多くが月収10万円以下(5万円以下の方も普通にいます)、時給換算すると200円とか300円という状況なのでしょうか。これでは、売れれば売れるほど苦しくなります。
作り手の皆さんとお話しすると、作るのが本当に好きで、「染めたり織ったりしている時が本当に楽しい」という言葉を良く聞きます。
僕はだからこそ、作る人達がもっと収入の事を考えなければいけないと思います。そして、適正な収入があり、安心してモノづくりができる仕組みを多種多様な人々が集まって構築する必要があると思います。
もう待ったなしで伝統や思いなど守るべきコトを業界として再確認した上で、変革の具体的アクションを起こす時です。
今のままだと、伝統を守るために未来が犠牲になっていると言っても過言ではありません。残すべき伝統を未来に繋ぎ、次の発展のための「変革」です。
2017年11月23日
【No.1523】産地としての転換期と僕らの役割
先週は、福岡県八女にあるうなぎの寝床さんの新たな拠点、旧寺崎邸でスタートした「沖縄 ちくごものづくり比較展」。このオープニングイベントで、沖縄の歴史と工芸+ゆいまーる沖縄の取組についてお話しさせてもらいました。

今週は、ゆいまーる沖縄主催の「沖縄型工房運営研究会」、連続セミナーの最終回でした。

そして、一昨日は石垣島へ、、
石垣みらいカレッジの講座で、「10年後の見据えた 沖縄型工房運営学」と題してセミナーを開催させてもらいました。

石垣島だけでなく、西表島、波照間島からも参加者の方々が。
ジャンルもやちむん、織物、木工、民具、そしてふんどし!まで様々でした。
懇親会も開いてもらい楽しい夜でしたー!

思うように売れなくて困っている他産地とは違い、沖縄は売れているのに工房運営が楽ではないという特徴があります。でも、なぜそのような状況なのか?どうすれば変えられるのか?誰に相談すればよいのか?
作り手の人達はそれが分からくて困っています。
僕自身も、ゆいまーる沖縄として、流通を通じて沖縄の工芸業界に貢献するというだけでは、業界の山積している課題を解決するのは不可能だと思い、作り手さん達へ向けた学びと交流の場として「沖縄型工房運営研究会」をスタートさせました。
(しかも、このアイデアはうちの社員から出たという事が僕にとってすごく嬉しかったのです!)
こうやって勉強会を通じて作り手のみなさんと話をしていると、沖縄のモノづくりも転換期を迎えているなとつくづく感じます。
モノづくりが転換期を迎えるという事は、ゆいまーる沖縄も転換期であるという事です。
そのために、沖縄型工房運営研究会や地域間交流を通じて、作り手の皆さん、そして今まで関わりのなかった人達と一緒に、これまでの枠組みにとらわれず、新たな立ち位置、役割を模索し、イノベーションへとつなげていきたいと思います。

今週は、ゆいまーる沖縄主催の「沖縄型工房運営研究会」、連続セミナーの最終回でした。

そして、一昨日は石垣島へ、、
石垣みらいカレッジの講座で、「10年後の見据えた 沖縄型工房運営学」と題してセミナーを開催させてもらいました。
石垣島だけでなく、西表島、波照間島からも参加者の方々が。
ジャンルもやちむん、織物、木工、民具、そしてふんどし!まで様々でした。
懇親会も開いてもらい楽しい夜でしたー!
思うように売れなくて困っている他産地とは違い、沖縄は売れているのに工房運営が楽ではないという特徴があります。でも、なぜそのような状況なのか?どうすれば変えられるのか?誰に相談すればよいのか?
作り手の人達はそれが分からくて困っています。
僕自身も、ゆいまーる沖縄として、流通を通じて沖縄の工芸業界に貢献するというだけでは、業界の山積している課題を解決するのは不可能だと思い、作り手さん達へ向けた学びと交流の場として「沖縄型工房運営研究会」をスタートさせました。
(しかも、このアイデアはうちの社員から出たという事が僕にとってすごく嬉しかったのです!)
こうやって勉強会を通じて作り手のみなさんと話をしていると、沖縄のモノづくりも転換期を迎えているなとつくづく感じます。
モノづくりが転換期を迎えるという事は、ゆいまーる沖縄も転換期であるという事です。
そのために、沖縄型工房運営研究会や地域間交流を通じて、作り手の皆さん、そして今まで関わりのなかった人達と一緒に、これまでの枠組みにとらわれず、新たな立ち位置、役割を模索し、イノベーションへとつなげていきたいと思います。
2017年11月04日
【No.1522】作り手が弱く、売り手が圧倒的に強いというパワーバランス
11月1日と2日、徳山大学 大田先生の企画で、
全国のテキスタイル産地で活動する人達が集まったミーティングに参加させてもらいました。
その中で、僕も沖縄染織の現状と、これからゆいまーる沖縄として取組んでいく事をお話しさせてもらいました。

沖縄のような手工芸の産地、そして機械生産の産地。
生産形態は様々な違いはあれど、生地の出荷単価を上げなければ、今後産地として成り立っていかないのは共通していますね。
沖縄の染織物の出荷価格があまりにも安いのと同じく、機械生産のテキスタイル産地もここまで安いのかと驚きました。とある機械生産の産地では、出荷価格が300円/m、店頭価格が3,000円〜4,000円/mという事でした。ちなみに、市場価格の約10%程度しか生産者に残らないというのは、原料供給型のスタイルに似ています。
この構造は呉服業界にもほぼあてはまりますね。生み出された付加価値の10%前後しか残らないのでは、産地が疲弊して当然です。
そして、この状況を生み出しているのが、作り手が弱く、売り手が圧倒的に強いというパワーバランスです。

この状況を変えるには、全体構造・ビジネスモデルの再編集をして、役割の変更と利益の再配分を行う事だと思います。
今までよりどんなに良いモノを作っても、モノと情報の流通といった全体像が変わらない限り、作り手、産地は良くならない。その事が改めてよく分かりました。
これからは、例えば流通がメーカー(作り手)機能を持つ、メーカー(作り手)が販売機能を持つといったように、1カ所が複数の役割を担っていくこと。
そして、これまで業界に関わりがなかった人や組織が繋がっていくこと。
そうする事によって、付加価値が上がり、さらに生み出された利益が適正に配分されていきます。
ゆいまーる沖縄としては、沖縄の染織ジャンルでこの考えを少しずつ実践していきます。そして、今回出会った全国のみなさんとも交流をしながら、検証していきたいと考えています。
全国のテキスタイル産地で活動する人達が集まったミーティングに参加させてもらいました。
その中で、僕も沖縄染織の現状と、これからゆいまーる沖縄として取組んでいく事をお話しさせてもらいました。

沖縄のような手工芸の産地、そして機械生産の産地。
生産形態は様々な違いはあれど、生地の出荷単価を上げなければ、今後産地として成り立っていかないのは共通していますね。
沖縄の染織物の出荷価格があまりにも安いのと同じく、機械生産のテキスタイル産地もここまで安いのかと驚きました。とある機械生産の産地では、出荷価格が300円/m、店頭価格が3,000円〜4,000円/mという事でした。ちなみに、市場価格の約10%程度しか生産者に残らないというのは、原料供給型のスタイルに似ています。
この構造は呉服業界にもほぼあてはまりますね。生み出された付加価値の10%前後しか残らないのでは、産地が疲弊して当然です。
そして、この状況を生み出しているのが、作り手が弱く、売り手が圧倒的に強いというパワーバランスです。

この状況を変えるには、全体構造・ビジネスモデルの再編集をして、役割の変更と利益の再配分を行う事だと思います。
今までよりどんなに良いモノを作っても、モノと情報の流通といった全体像が変わらない限り、作り手、産地は良くならない。その事が改めてよく分かりました。
これからは、例えば流通がメーカー(作り手)機能を持つ、メーカー(作り手)が販売機能を持つといったように、1カ所が複数の役割を担っていくこと。
そして、これまで業界に関わりがなかった人や組織が繋がっていくこと。
そうする事によって、付加価値が上がり、さらに生み出された利益が適正に配分されていきます。
ゆいまーる沖縄としては、沖縄の染織ジャンルでこの考えを少しずつ実践していきます。そして、今回出会った全国のみなさんとも交流をしながら、検証していきたいと考えています。
2017年10月22日
【No.1521】秋田にて・・地域間交流と課題解決、そして新たな価値創造へ
今週は3日間秋田へ出張でした。
See Visionsの東海林さんにお世話になり、亀の町ストアでトークショーをさせていただき、
翌日には、樺細工、漆器、焼物といった、秋田の工芸品の工房等を案内していただきました。


最終日は秋田公立美術大学で、沖縄工芸業界の現状と、ゆいまーる沖縄の取組みについて
お話しをさせていただきました。

地域特有の課題もあるのですが、やっぱり共通する課題は多いです。
それらを解決する1つの手段として、地域間の交流をしながら、
作り手、売り手、クリエイター、学生、先生、行政など、
多種多様な人々が開かれた対話とアクションを起こすことが重要だなと思っています。
もう、今までのような経済成長を前提とした価値観や手法は通用しないと思います。
成熟した社会をどう生きていくのか。
これからを生きていくための価値観の転換と、新たな価値創造が必要です。
特に人口減少が日本一の秋田県。
2025年ごろから人口が減少していくと予想されている沖縄県も秋田県から学ぶ事は多いと思います。

そんなわけで。ぜひ今後は沖縄と秋田の地域間交流も継続したいと思いますし、
それ以外の地域との交流も行っていきたいと考えています。
See Visionsの東海林さんにお世話になり、亀の町ストアでトークショーをさせていただき、
翌日には、樺細工、漆器、焼物といった、秋田の工芸品の工房等を案内していただきました。


最終日は秋田公立美術大学で、沖縄工芸業界の現状と、ゆいまーる沖縄の取組みについて
お話しをさせていただきました。

地域特有の課題もあるのですが、やっぱり共通する課題は多いです。
それらを解決する1つの手段として、地域間の交流をしながら、
作り手、売り手、クリエイター、学生、先生、行政など、
多種多様な人々が開かれた対話とアクションを起こすことが重要だなと思っています。
もう、今までのような経済成長を前提とした価値観や手法は通用しないと思います。
成熟した社会をどう生きていくのか。
これからを生きていくための価値観の転換と、新たな価値創造が必要です。
特に人口減少が日本一の秋田県。
2025年ごろから人口が減少していくと予想されている沖縄県も秋田県から学ぶ事は多いと思います。

そんなわけで。ぜひ今後は沖縄と秋田の地域間交流も継続したいと思いますし、
それ以外の地域との交流も行っていきたいと考えています。
2017年10月08日
【No.1520】業界を再編集する時
最近、沖縄の染織関係者と話をする機会が多くなりました。
まだまだ染織業界は分からないことが多いのですが、
少しずつ業界の課題が見えてきました。
中でも大きなものは後継者をいかに確保、育成するのかという事です。
現場では世代交代の波がジワジワ押し寄せていて、
沖縄の産地によっては、今後20年で70%前後の作り手が引退するところもあります。
これから未来を担う40代以下の若手が圧倒的に少ないのです。

では、そもそもなぜこのなよう状況になってしまったのか?
原因はいくつもありますが、
僕が一番大きいと思うのが、やっぱりモノづくりの労働に対する収入の低さです。
そして、この労働と収入の格差を生み出しているのが、呉服市場の流通構造にあると思うのです。
工芸業界の中でも特に昔からの慣習が色濃く残っている呉服市場。
僕は、業界の中のどこそこがよくない!とは思っていません。
ただ、作り手、問屋、売り手といった各工程の多くが厳しいという事は、
やっぱり全体の構造に問題があると思うのです。
他の業界を見渡すと、昔からある独自の業界構造、利権が絡んでいる業界など、、
しがらみいっぱいのビジネスモデルは行き詰まりをみせています。
という事は、
関係者がハッピーになるように業界を再編集するしかないのです。
沖縄の工芸でいうと、特に染織業界です。
関係者みんなが、それぞれの権利を守るという視点ではなく、
作り手、売り手、そして使い手がどうしたらハッピーになれるのか?
という視点で前向きな議論と、未来に向けた具体的なアクションをスタートさせる必要があります。
ゆいまーる沖縄も、染織業界を再編集するための取組みを少しずつ実践していきたいと思います。
まだまだ染織業界は分からないことが多いのですが、
少しずつ業界の課題が見えてきました。
中でも大きなものは後継者をいかに確保、育成するのかという事です。
現場では世代交代の波がジワジワ押し寄せていて、
沖縄の産地によっては、今後20年で70%前後の作り手が引退するところもあります。
これから未来を担う40代以下の若手が圧倒的に少ないのです。

では、そもそもなぜこのなよう状況になってしまったのか?
原因はいくつもありますが、
僕が一番大きいと思うのが、やっぱりモノづくりの労働に対する収入の低さです。
そして、この労働と収入の格差を生み出しているのが、呉服市場の流通構造にあると思うのです。
工芸業界の中でも特に昔からの慣習が色濃く残っている呉服市場。
僕は、業界の中のどこそこがよくない!とは思っていません。
ただ、作り手、問屋、売り手といった各工程の多くが厳しいという事は、
やっぱり全体の構造に問題があると思うのです。
他の業界を見渡すと、昔からある独自の業界構造、利権が絡んでいる業界など、、
しがらみいっぱいのビジネスモデルは行き詰まりをみせています。
という事は、
関係者がハッピーになるように業界を再編集するしかないのです。
沖縄の工芸でいうと、特に染織業界です。
関係者みんなが、それぞれの権利を守るという視点ではなく、
作り手、売り手、そして使い手がどうしたらハッピーになれるのか?
という視点で前向きな議論と、未来に向けた具体的なアクションをスタートさせる必要があります。
ゆいまーる沖縄も、染織業界を再編集するための取組みを少しずつ実践していきたいと思います。
2017年10月01日
【No.1519】沖縄型工房運営研究会の連続セミナーがスタートしました!
昨日から沖縄型工房運営研究会の連続セミナーがスタートしました。
今回も焼物、染、織、ガラス、木工など幅広いジャンルの作り手の方々に
お越しいただきました。
定員を超えるお申込があり、途中で募集を締切る形になってしまいました。
後からお申込する予定だった皆さん、本当にごめんなさい!

今回のテーマは、
「工房運営の現状と未来を考えよう/工房の事業計画作成について」。
5年後、10年後にどんな工房にしたいのか?、損益計算書の読み方、
直販・卸の売上バランスについて、5年計画作成のポイントと事例などについて
お話しさせていただきました。
まずは売上ではなく粗利益の重要性について、ワークも交えて学びます。

勿論直販すると粗利益は高いです。
しかし沖縄の工房の場合、1人2人といった少人数で工房運営しているケースが
ほとんどで、そうなると職人さんの手が止まり、ある時点から売上が伸びなくなります。
工房さんの状況に応じて、直販と卸をどう組み合わせれば粗利が最大になるのか?
その考え方も学びます。

こういったいくつかの考え方を学んだ後に、5年計画書に思いと数字を落し込んでいきます。

当たり前ですが、原価が分からなければ、粗利益額と粗利益率は明らかになりません。
という事で、次回はいよいよ原価計算と価格設定について学びます。
第2回目は10月ですが、これから日程はお知らせいたします!
単発でもお申込できますので、お気軽にお問い合わせください。
今回も焼物、染、織、ガラス、木工など幅広いジャンルの作り手の方々に
お越しいただきました。
定員を超えるお申込があり、途中で募集を締切る形になってしまいました。
後からお申込する予定だった皆さん、本当にごめんなさい!

今回のテーマは、
「工房運営の現状と未来を考えよう/工房の事業計画作成について」。
5年後、10年後にどんな工房にしたいのか?、損益計算書の読み方、
直販・卸の売上バランスについて、5年計画作成のポイントと事例などについて
お話しさせていただきました。
まずは売上ではなく粗利益の重要性について、ワークも交えて学びます。

勿論直販すると粗利益は高いです。
しかし沖縄の工房の場合、1人2人といった少人数で工房運営しているケースが
ほとんどで、そうなると職人さんの手が止まり、ある時点から売上が伸びなくなります。
工房さんの状況に応じて、直販と卸をどう組み合わせれば粗利が最大になるのか?
その考え方も学びます。

こういったいくつかの考え方を学んだ後に、5年計画書に思いと数字を落し込んでいきます。

当たり前ですが、原価が分からなければ、粗利益額と粗利益率は明らかになりません。
という事で、次回はいよいよ原価計算と価格設定について学びます。
第2回目は10月ですが、これから日程はお知らせいたします!
単発でもお申込できますので、お気軽にお問い合わせください。
2017年09月23日
【No.1518】沖縄型工房運営研究会の次なる取組み
7月から単発で開催していた沖縄型工房運営研究会のセミナー。

現在、売上が厳しい、逆によく売れている・・状況は様々です。
しかし、それぞれの作り手の方に共通しているのが、収益の低さと将来に対する不安です。
何となくモヤモヤしているけど、どこに問題があるのかがよく分からない。
そういった状況だったのが、セミナー終了後にはどこに問題があるのかが
明らかになってきます。
セミナーに参加された工房さんから「もっと詳しく学びたい」という声をいただき、
いよいよ連続勉強会をスタートさせる事になりました。

今回の「沖縄型工房運営研究会 連続セミナー」は、
第1回「工房運営の現状と未来を考えよう/工房の事業計画作成について」という事で、
5年後、10年後にどんな工房にしたいのか?、損益計算書の読み方、
直販・卸の売上バランスについて、
5年計画作成のポイントと事例について一緒に学んでいきます。
そして、2回目以降の内容は、
・第2回:10月予定
「数字のポイントをおさえるだけで工房運営は変わる!:原価計算、販売価格の決め方」
・第3回:11月予定
「お金をかけずに行う工房のブランド構築とPR:ブランディング構築とSNS活用」
となっています。
さらに、11月21日は石垣島でも単発ですが勉強会を開催させていただく事になりました。
10月に開講する「石垣みらいカレッジ」のプログラムに入っています。


11月21日(火)18:30〜20:30 です。
石垣島の作り手のみなさん、ぜひぜひお越しください!

現在、売上が厳しい、逆によく売れている・・状況は様々です。
しかし、それぞれの作り手の方に共通しているのが、収益の低さと将来に対する不安です。
何となくモヤモヤしているけど、どこに問題があるのかがよく分からない。
そういった状況だったのが、セミナー終了後にはどこに問題があるのかが
明らかになってきます。
セミナーに参加された工房さんから「もっと詳しく学びたい」という声をいただき、
いよいよ連続勉強会をスタートさせる事になりました。

今回の「沖縄型工房運営研究会 連続セミナー」は、
第1回「工房運営の現状と未来を考えよう/工房の事業計画作成について」という事で、
5年後、10年後にどんな工房にしたいのか?、損益計算書の読み方、
直販・卸の売上バランスについて、
5年計画作成のポイントと事例について一緒に学んでいきます。
そして、2回目以降の内容は、
・第2回:10月予定
「数字のポイントをおさえるだけで工房運営は変わる!:原価計算、販売価格の決め方」
・第3回:11月予定
「お金をかけずに行う工房のブランド構築とPR:ブランディング構築とSNS活用」
となっています。
さらに、11月21日は石垣島でも単発ですが勉強会を開催させていただく事になりました。
10月に開講する「石垣みらいカレッジ」のプログラムに入っています。


11月21日(火)18:30〜20:30 です。
石垣島の作り手のみなさん、ぜひぜひお越しください!
2017年09月05日
【No.1517】旧盆、ウークイはお休みします!
今日は旧暦7月15日、旧盆のウークイです。
一昨日、旧暦7月13日(ウンケー)に迎えた先祖の霊を、
満月の晩(旧暦7月15日)にグソー(あの世)に帰ります。

沖縄の学校も自治体によってお休みのところがありますが、
ゆいまーる沖縄も去年からウークイをお休みにしました。
会社の経営目的の1つに、
「琉球の文化・祈りに深く学び、それを事業にする」
という一文がありますが、
沖縄でも大切な日は会社もお休みにして、
県内に実家のある社員は、行事のお手伝い、ご先祖様をしっかり送れるように。
そして、県外出身の社員は、
各地で行われるエイサーを観に行ったり旧盆を体感できる日にしてほしいと思っています。
お客さまにはご迷惑をおかけいたしますが、
沖縄にとって大切な年中行事の1つという事で、ご理解いただければと思います。
一昨日、旧暦7月13日(ウンケー)に迎えた先祖の霊を、
満月の晩(旧暦7月15日)にグソー(あの世)に帰ります。

沖縄の学校も自治体によってお休みのところがありますが、
ゆいまーる沖縄も去年からウークイをお休みにしました。
会社の経営目的の1つに、
「琉球の文化・祈りに深く学び、それを事業にする」
という一文がありますが、
沖縄でも大切な日は会社もお休みにして、
県内に実家のある社員は、行事のお手伝い、ご先祖様をしっかり送れるように。
そして、県外出身の社員は、
各地で行われるエイサーを観に行ったり旧盆を体感できる日にしてほしいと思っています。
お客さまにはご迷惑をおかけいたしますが、
沖縄にとって大切な年中行事の1つという事で、ご理解いただければと思います。
2017年08月12日
【No.1516】「作り手を生かさず殺さず」という恐ろしい言葉・・・
先週は作り手のみなさんの所へ行く時間が多い1週間でした。
昼は工房さんへ、染め、織り、木工と様々なジャンルの作り手さんと
次なる展開に向けてお話しをしてきました。

夜は三線組合さんからのご依頼で、工房運営の勉強会も行いました。


流通している三線の約75%は海外産といわれているこの業界。
加えて、ほとんどが親方一人で工房運営をしているので、後継者不足も深刻です。
今週色々話をしていて特に気になったのが、やっぱり呉服業界の流通についてです。
モノづくりを始めて数十年になる大御所の作り手さんが言っていました。
今の呉服業界は、「作り手を生かさず、殺さず」といった構造になっている。
僕も同感です。
しかも、同じような言葉を他の何名もの作り手さんから聞いた事があります。
今どき作り手が独自で販売しようものなら流通側から圧力が掛かるなんてありえない!
長い間、染め、織りをしている作り手の方からは、
「これまでの呉服業界の流通にはお世話になってきたから・・」と良く聞きます。
もちろん、これまで買い続けてもらった事に対する感謝は必要ですが、
今は、未来をどうするかを業界の人達は本気で考えなければいけないと思います。
生産量も限界な上に、今の価格でどんなに買い取ってもらっても、
作り手の暮らしは苦しいままなのです。
しかも、世代交代までもう時間がありません。
作り手と流通は対等な関係でなければいけません。
今は流通側があまりにも強すぎます。
沖縄の工芸業界全体ですが、、
特に染織の作り手のみなさん、変革に向けてもう動き出しましょう。
8月19日にまた勉強会も行います。
ご自分の工房運営もそうですが、業界も何とかしなければ!
と思っている作り手のみなさんもぜひご参加ください。

昼は工房さんへ、染め、織り、木工と様々なジャンルの作り手さんと
次なる展開に向けてお話しをしてきました。

夜は三線組合さんからのご依頼で、工房運営の勉強会も行いました。


流通している三線の約75%は海外産といわれているこの業界。
加えて、ほとんどが親方一人で工房運営をしているので、後継者不足も深刻です。
今週色々話をしていて特に気になったのが、やっぱり呉服業界の流通についてです。
モノづくりを始めて数十年になる大御所の作り手さんが言っていました。
今の呉服業界は、「作り手を生かさず、殺さず」といった構造になっている。
僕も同感です。
しかも、同じような言葉を他の何名もの作り手さんから聞いた事があります。
今どき作り手が独自で販売しようものなら流通側から圧力が掛かるなんてありえない!
長い間、染め、織りをしている作り手の方からは、
「これまでの呉服業界の流通にはお世話になってきたから・・」と良く聞きます。
もちろん、これまで買い続けてもらった事に対する感謝は必要ですが、
今は、未来をどうするかを業界の人達は本気で考えなければいけないと思います。
生産量も限界な上に、今の価格でどんなに買い取ってもらっても、
作り手の暮らしは苦しいままなのです。
しかも、世代交代までもう時間がありません。
作り手と流通は対等な関係でなければいけません。
今は流通側があまりにも強すぎます。
沖縄の工芸業界全体ですが、、
特に染織の作り手のみなさん、変革に向けてもう動き出しましょう。
8月19日にまた勉強会も行います。
ご自分の工房運営もそうですが、業界も何とかしなければ!
と思っている作り手のみなさんもぜひご参加ください。

2017年08月06日
【No.1515】工房の5年後、10年後を考える
新ニーズモデル事業も県外視察が終わり、いよいよ工房さんの個別訪問がスタートしました。
今回は離島からスタートという事で石垣島へ。。


それぞれの工房さんとじっくりミーティングをしてきました。
この事業では商品開発を行うのですが、実はポイントにしているのは商品開発ではありません。
商品を開発するプロセスの中で、工房の未来像を描き、数字で現状把握・計画を作成、
そして、流通計画、原価計算、売価設定を、
工房運営が良くなるように再構築していく事を重要視しています。
まず最初にやるのが、未来像を描くこと。
工房の10年後のビジョン、そして5年計画を作ります。
その時に「思い」と「数字」を一緒に考えます。
5年後、10年後、工房をどうしていきたいのか?
工房さんそれぞれにシアワセのスタイルも異なります。
これをまず明確にする。
ここが重要です!
そして、その後に商品、価格、流通、PRをどうしていくのかを
具体的に設計していきます。
さぁ、いよいよスタートです!
工房のみなさん、よろしくお願いします!!
↓ ↓ ここからお知らせです ↓ ↓
ちなみに、この事業でやっているプログラムをアレンジした「沖縄型工房運営セミナー」。
前回は満席で、来られなかった工房さんもいましたので、
急遽8月も第2回目を実施する事になりました。
ご希望の工房さん、お気軽にお申し込みください!

今回は離島からスタートという事で石垣島へ。。


それぞれの工房さんとじっくりミーティングをしてきました。
この事業では商品開発を行うのですが、実はポイントにしているのは商品開発ではありません。
商品を開発するプロセスの中で、工房の未来像を描き、数字で現状把握・計画を作成、
そして、流通計画、原価計算、売価設定を、
工房運営が良くなるように再構築していく事を重要視しています。
まず最初にやるのが、未来像を描くこと。
工房の10年後のビジョン、そして5年計画を作ります。
その時に「思い」と「数字」を一緒に考えます。
5年後、10年後、工房をどうしていきたいのか?
工房さんそれぞれにシアワセのスタイルも異なります。
これをまず明確にする。
ここが重要です!
そして、その後に商品、価格、流通、PRをどうしていくのかを
具体的に設計していきます。
さぁ、いよいよスタートです!
工房のみなさん、よろしくお願いします!!
↓ ↓ ここからお知らせです ↓ ↓
ちなみに、この事業でやっているプログラムをアレンジした「沖縄型工房運営セミナー」。
前回は満席で、来られなかった工房さんもいましたので、
急遽8月も第2回目を実施する事になりました。
ご希望の工房さん、お気軽にお申し込みください!

2017年07月31日
【No.1514】工房向けの勉強会開催しました!
昨日は、ゆいまーる沖縄 本店で初の開催となる工房運営の勉強会を行いました。
日曜日の夕方にも関わらず満席で、本当にたくさんの作り手や
関係者のみなさんにお越しいただきました。
本当にありがとうございます!

質疑応答でもかなり突っ込んだ質問やご意見をいただき、
とても濃い中身だったと思います。

早速、もっと深く原価計算や価格設定について学びたいという方や、
今回来られなかったので、次回は行きたいという声をいただいています。
まずは同じ内容で再度勉強会の開催を来月も実施します。
そして、市場の動向、原価計算、価格設定、工房の事業計画づくりなど、
1つひとつの項目を深掘りしていく連続勉強会も計画していますので、もう少しお待ち下さい。

僕も昨日の勉強会を開催して、
工房さんの売上・収益が向上し、一人でも多くの作り手が増えることで、
「工芸の島沖縄」の更なる発展に寄与していきたいという思いを再認識することができました。
日曜日の夕方にも関わらず満席で、本当にたくさんの作り手や
関係者のみなさんにお越しいただきました。
本当にありがとうございます!

質疑応答でもかなり突っ込んだ質問やご意見をいただき、
とても濃い中身だったと思います。

早速、もっと深く原価計算や価格設定について学びたいという方や、
今回来られなかったので、次回は行きたいという声をいただいています。
まずは同じ内容で再度勉強会の開催を来月も実施します。
そして、市場の動向、原価計算、価格設定、工房の事業計画づくりなど、
1つひとつの項目を深掘りしていく連続勉強会も計画していますので、もう少しお待ち下さい。

僕も昨日の勉強会を開催して、
工房さんの売上・収益が向上し、一人でも多くの作り手が増えることで、
「工芸の島沖縄」の更なる発展に寄与していきたいという思いを再認識することができました。
2017年07月30日
【No.1513】沖縄県立芸術大学との取組み vol.2
この数年新たな価値創造に向けて、多種多様な繋がりを作ってきましたが、
そのひとつである沖縄県立芸術大学との取組み。
昨年度は、初めての商品開発で沖縄デザインブランドの「シマノネ」を立ち上げ、
その後の販売も好評です!
今回は、デザイン課の「イラストレーション」の授業で協力をさせていただきました。
テーマは「ゆいまーる沖縄にないものをイラストレーションを活用して提案する」です。
何とも面白そうなテーマ!
ゆいまーる沖縄の会社見学からスタート。
その後、別の日には僕の講話を行いました。
そして最終日は学生皆さんが考えた事をイラストレーションにしてプレゼンです。

さすが芸大生!
とっても面白い企画がたくさん出ました!
今回は製品化が目的ではなく、あくまで授業なのですが、
実現できるものがあれば、ぜひカタチにしてみたいなーと思っています。
みなさん、本当にありがとうございました!

そのひとつである沖縄県立芸術大学との取組み。
昨年度は、初めての商品開発で沖縄デザインブランドの「シマノネ」を立ち上げ、
その後の販売も好評です!
今回は、デザイン課の「イラストレーション」の授業で協力をさせていただきました。
テーマは「ゆいまーる沖縄にないものをイラストレーションを活用して提案する」です。
何とも面白そうなテーマ!
ゆいまーる沖縄の会社見学からスタート。
その後、別の日には僕の講話を行いました。
そして最終日は学生皆さんが考えた事をイラストレーションにしてプレゼンです。

さすが芸大生!
とっても面白い企画がたくさん出ました!
今回は製品化が目的ではなく、あくまで授業なのですが、
実現できるものがあれば、ぜひカタチにしてみたいなーと思っています。
みなさん、本当にありがとうございました!

2017年07月17日
【No.1512】工房運営の勉強会を開催します
先日の琉球新報に、沖縄工芸品に関する記事が掲載されていました。
生産額はピーク時の3割減、事業者数は半減との事。
生産額については、途中で知花花織、三線が追加されているので、
もっと減っている事になります。

記事では需要減少となっていますが、
漆器以外の業界は、生産に対して供給が追いついていないのが現状です。
商品供給が間に合っていなければ、作る人や事業所も増えるはずです。
なのになぜ事業所も減り、生産額が落ちるのか?
この現象が起きている根本的な問題、
それは、作り手の労働に対する収入の低さです。
ここを解決しないと作り手も増えません。
ゆいまーる沖縄は、作り手の皆さんからの商品仕入れや
行政の事業等を通じて微力ながらこの問題解決に向けた取組みをしてきました。
それでも全然アクションは足りません。
そこで今回、社員からも提案があり、独自に工房さん向けの勉強会を実施する事にしました。

今回は単発での開催ですが、
今後は市場の動向、原価計算、価格設定、工房の事業計画づくりなど
細かなプログラムを作っていきたいと考えています。
ゆいまーる沖縄としても、この勉強会は利益を生む事業ではありません。
なので、プログラムづくりや運営のための費用の一部はいただく形で、
工房さんの負担はなるべく少なくなるようにしています。
関心のある作り手のみなさん、ぜひお気軽にご連絡ください。
▼詳細とお申し込みについてはこちらからどうぞ▼
https://www.facebook.com/events/125802494686384/?active_tab=about
沖縄はものづくりの島とも呼ばれるほど、かつてから手仕事を生業としている方が多くいます。昨今は、日本製、手しごとが全国的に注目され、沖縄の工芸品も市場の需要に対して供給が間に合わない状況が続いています。しかし、業界全体として、労働に対する収入の少なさ、社会保障が整備されていない、後継者がいないといった課題が多いのも事実です。今回のプチセミナーは、未来を見据えた工房運営に大切な視点や、原価計算・価格設定のポイントを解説、流通の役割を通して見てきた工芸業界と市場の現状と見通しを共有し、今後10年後を見据えた工房運営についてお話をさせていただきます。
---------- タイトル ----------
10年後を見据えた工房運営について考える
-------- 日程等詳細 --------
[日時] 7月30日(日) 17:00-19:00
[参加費] お一人様 1,500円
[お申し込み]
* 要予約となっております。
* お電話、Facebookメッセージ、店頭にて受け付けます。
* 本イベントページにて参加ボタンを押しただけではご予約となりませんのでご了承ください。
* Facebookメッセージにてご連絡の場合は、営業日に確認の上ご返信申し上げます。
-------- 講師紹介 --------
鈴木修司
ゆいまーる沖縄(株)代表取締役社長。
琉球ガラス生産・販場協同組合理事、沖縄県工芸産業振興審議会委員。
---------- お問い合わせ先 ----------
ゆいまーる沖縄 本店
営業時間 11:00-18:00
定休日 木曜
tel 098-882-6995
担当 西谷、嘉陽
生産額はピーク時の3割減、事業者数は半減との事。
生産額については、途中で知花花織、三線が追加されているので、
もっと減っている事になります。

記事では需要減少となっていますが、
漆器以外の業界は、生産に対して供給が追いついていないのが現状です。
商品供給が間に合っていなければ、作る人や事業所も増えるはずです。
なのになぜ事業所も減り、生産額が落ちるのか?
この現象が起きている根本的な問題、
それは、作り手の労働に対する収入の低さです。
ここを解決しないと作り手も増えません。
ゆいまーる沖縄は、作り手の皆さんからの商品仕入れや
行政の事業等を通じて微力ながらこの問題解決に向けた取組みをしてきました。
それでも全然アクションは足りません。
そこで今回、社員からも提案があり、独自に工房さん向けの勉強会を実施する事にしました。

今回は単発での開催ですが、
今後は市場の動向、原価計算、価格設定、工房の事業計画づくりなど
細かなプログラムを作っていきたいと考えています。
ゆいまーる沖縄としても、この勉強会は利益を生む事業ではありません。
なので、プログラムづくりや運営のための費用の一部はいただく形で、
工房さんの負担はなるべく少なくなるようにしています。
関心のある作り手のみなさん、ぜひお気軽にご連絡ください。
▼詳細とお申し込みについてはこちらからどうぞ▼
https://www.facebook.com/events/125802494686384/?active_tab=about
沖縄はものづくりの島とも呼ばれるほど、かつてから手仕事を生業としている方が多くいます。昨今は、日本製、手しごとが全国的に注目され、沖縄の工芸品も市場の需要に対して供給が間に合わない状況が続いています。しかし、業界全体として、労働に対する収入の少なさ、社会保障が整備されていない、後継者がいないといった課題が多いのも事実です。今回のプチセミナーは、未来を見据えた工房運営に大切な視点や、原価計算・価格設定のポイントを解説、流通の役割を通して見てきた工芸業界と市場の現状と見通しを共有し、今後10年後を見据えた工房運営についてお話をさせていただきます。
---------- タイトル ----------
10年後を見据えた工房運営について考える
-------- 日程等詳細 --------
[日時] 7月30日(日) 17:00-19:00
[参加費] お一人様 1,500円
[お申し込み]
* 要予約となっております。
* お電話、Facebookメッセージ、店頭にて受け付けます。
* 本イベントページにて参加ボタンを押しただけではご予約となりませんのでご了承ください。
* Facebookメッセージにてご連絡の場合は、営業日に確認の上ご返信申し上げます。
-------- 講師紹介 --------
鈴木修司
ゆいまーる沖縄(株)代表取締役社長。
琉球ガラス生産・販場協同組合理事、沖縄県工芸産業振興審議会委員。
---------- お問い合わせ先 ----------
ゆいまーる沖縄 本店
営業時間 11:00-18:00
定休日 木曜
tel 098-882-6995
担当 西谷、嘉陽
2017年07月09日
【No.1511】沖縄三線のブランド化に向けて
先週木曜日に、沖縄三線のブランド化の委員会が行われました。

僕も委員として参加させていただいていますが、
今回は、沖縄工芸の現状と課題、そして未来へ向けた取組みについてお話しさせていただきました。
工芸のジャンルは違えど、職人の所得、社会保障、後継者問題等は三線業界も同じ状況です。

業界として最も大きな危機は、この10〜15年で起こる世代交代です。
とにかく次世代の職人が相当少ないので、
産地によっては70〜80%の職人がいなくなってしまい、一気に人数、生産数が減少します。
そのためにも、ブランド力向上、モノづくりの付加価値アップ、そして職人の所得改善、
社会保障の整備をしていかなければなりません。
新商品開発や販路開拓で解決するような簡単な問題ではありません。
業界の構造改革が必要なのです。
5年〜10年という長い時間が掛かります。
もう動かないといけません!
いつやるのか?
今でしょ!
なのです!!
残された時間はもうないので、
僕も事業とは別に、そして事業ともうまく連動させながら、
工芸業界のためにできる限り時間を費やそうと思います。

僕も委員として参加させていただいていますが、
今回は、沖縄工芸の現状と課題、そして未来へ向けた取組みについてお話しさせていただきました。
工芸のジャンルは違えど、職人の所得、社会保障、後継者問題等は三線業界も同じ状況です。

業界として最も大きな危機は、この10〜15年で起こる世代交代です。
とにかく次世代の職人が相当少ないので、
産地によっては70〜80%の職人がいなくなってしまい、一気に人数、生産数が減少します。
そのためにも、ブランド力向上、モノづくりの付加価値アップ、そして職人の所得改善、
社会保障の整備をしていかなければなりません。
新商品開発や販路開拓で解決するような簡単な問題ではありません。
業界の構造改革が必要なのです。
5年〜10年という長い時間が掛かります。
もう動かないといけません!
いつやるのか?
今でしょ!
なのです!!
残された時間はもうないので、
僕も事業とは別に、そして事業ともうまく連動させながら、
工芸業界のためにできる限り時間を費やそうと思います。
2017年06月24日
【No.1510】6月23日 慰霊の日と想像力
昨日は6月23日、慰霊の日でした。
毎年、ゆいまーる沖縄のメンバーで糸満市にある魂魄の塔へ行くのですが、
今年は、地元南風原で沖縄戦を学ぶというプログラムにしたので、
明け方に平和祈念公園に家族で行ってきました。

平和の礎には、朝早くから沢山の方々が訪れて、祈りを捧げていました。

沖縄戦で亡くなった家族、親戚、友人、会った事のないオジー、オバ−といった祖先・・
それぞれの立場で、それぞれの思いを持ってここへやって来ます。

慰霊の日のような節目の時は、こうやって過去や他者に思いを馳せ、
今をどう生き、未来へこの平和を繋いでいくのかを考える日だと思います。
その時に、過去や未来といった時間軸、そして他者に対して、
どこまで想像力を働かせることができるのかがとても大事になってきます。
今の世の中を見ると、今が良ければ、自分さえ良ければ、といった風潮が強く、
他者や未来に対しての想像力が欠落していると思います。
例えば、沖縄に集中している米軍基地について、
沖縄とヤマトの温度差が依然として大きいのもその1つ。
戦後72年が経過し、戦争体験者がどんどん減っていく中で、
私たちには、他者や広い時間軸に対する想像力が求められているのではないでしょうか。
*6月4日の琉球新報で、こんな書評も書かせてもらいましたのでご覧下さい。

つながりをとりもどそう
「愚行」とは、文字通りおろかな行為のことである。この本には、戦争、弾圧、貧困、環境破壊、核、原発といった世界中で起きている愚行の数々が紹介されており、これら愚行を招いた要因が、資本主義の「速度と効率の追求」、「他者への想像力の欠如」、そして「他者の、ときに自らの記憶の破壊と忘却」であると書かれている。
本来、資本主義はより良い社会を築くための仕組みであったはずであるが、人間によるあくなき欲望の追求の結果、世界中で様々なひずみが発生している。沖縄は、第二次大戦時に地上戦を経験し、現在も米軍基地の過重な負担を強いられており、戦争という愚行の影響を受け続けている地域のひとつである。私はちょうど20年前に沖縄で暮らしはじめたが、沖縄に集中する米軍基地の現状を目の当たりにし、基地や戦争について今まで以上に考えるようになった。
戦争については、そもそも「戦争がなぜ起きるのか?」という背景を知る事が重要だが、その1つは現代資本主義の構造にあると思う。世界的な人口増加、エネルギー問題、富の集中と格差の拡大など、資本主義は行き詰まり感をみせているが、それでも過度な経済成長を追い続ける。ひとたび戦争が起きれば、軍需産業によって利潤を得る人や企業が存在し、私たちの暮らしにも影響を与える。
戦争によって遠い地域で苦しむ人々の様子をテレビや雑誌、ネットを通じて観る時、戦争の悲惨さや残酷さは感じても、戦争と自分達の暮らしの関係性については、想像力が働いていない事が多い。私はそのような状況を見て、経済はグローバルにつながっているが、人々の心は分断されているように思えてならない。
遠い地域で暮らす人々、さらに子や孫の世代といった未来の人々に思いをはせ、想像力を働かせる行為は、「今後どのように豊かになっていけば良いのか」を考えるきっかけになる。これまでのような金と物が中心の豊かさではなく、心をベースとした豊かさへの価値転換が求められている。
ご存じの通り、沖縄には「ゆいまーる」という言葉があり、かつては親族や集落の人々が集まり、農作業など労働交換の時にこの言葉が使われていた。今でも助け合いや、つながり、共同体といった意味合いで、沖縄の人々に受け継がれている。
沖縄では、このような人々とのつながり、そして自然や祖先とのつながりを大切にしている。この「つながり」は、自分は生かされているという価値観にも通じる重要なキーワードである。
世界で起きている愚行を少しでも減らしていくためには、自然、地域、人々がつながりを取り戻していく事が必要である。そのために、沖縄は本来持っている心をベースとした豊かさを発信する重要な役割を担っている地域である。
(鈴木修司・ゆいまーる沖縄代表取締役社長)
毎年、ゆいまーる沖縄のメンバーで糸満市にある魂魄の塔へ行くのですが、
今年は、地元南風原で沖縄戦を学ぶというプログラムにしたので、
明け方に平和祈念公園に家族で行ってきました。
平和の礎には、朝早くから沢山の方々が訪れて、祈りを捧げていました。

沖縄戦で亡くなった家族、親戚、友人、会った事のないオジー、オバ−といった祖先・・
それぞれの立場で、それぞれの思いを持ってここへやって来ます。
慰霊の日のような節目の時は、こうやって過去や他者に思いを馳せ、
今をどう生き、未来へこの平和を繋いでいくのかを考える日だと思います。
その時に、過去や未来といった時間軸、そして他者に対して、
どこまで想像力を働かせることができるのかがとても大事になってきます。
今の世の中を見ると、今が良ければ、自分さえ良ければ、といった風潮が強く、
他者や未来に対しての想像力が欠落していると思います。
例えば、沖縄に集中している米軍基地について、
沖縄とヤマトの温度差が依然として大きいのもその1つ。
戦後72年が経過し、戦争体験者がどんどん減っていく中で、
私たちには、他者や広い時間軸に対する想像力が求められているのではないでしょうか。
*6月4日の琉球新報で、こんな書評も書かせてもらいましたのでご覧下さい。

つながりをとりもどそう
「愚行」とは、文字通りおろかな行為のことである。この本には、戦争、弾圧、貧困、環境破壊、核、原発といった世界中で起きている愚行の数々が紹介されており、これら愚行を招いた要因が、資本主義の「速度と効率の追求」、「他者への想像力の欠如」、そして「他者の、ときに自らの記憶の破壊と忘却」であると書かれている。
本来、資本主義はより良い社会を築くための仕組みであったはずであるが、人間によるあくなき欲望の追求の結果、世界中で様々なひずみが発生している。沖縄は、第二次大戦時に地上戦を経験し、現在も米軍基地の過重な負担を強いられており、戦争という愚行の影響を受け続けている地域のひとつである。私はちょうど20年前に沖縄で暮らしはじめたが、沖縄に集中する米軍基地の現状を目の当たりにし、基地や戦争について今まで以上に考えるようになった。
戦争については、そもそも「戦争がなぜ起きるのか?」という背景を知る事が重要だが、その1つは現代資本主義の構造にあると思う。世界的な人口増加、エネルギー問題、富の集中と格差の拡大など、資本主義は行き詰まり感をみせているが、それでも過度な経済成長を追い続ける。ひとたび戦争が起きれば、軍需産業によって利潤を得る人や企業が存在し、私たちの暮らしにも影響を与える。
戦争によって遠い地域で苦しむ人々の様子をテレビや雑誌、ネットを通じて観る時、戦争の悲惨さや残酷さは感じても、戦争と自分達の暮らしの関係性については、想像力が働いていない事が多い。私はそのような状況を見て、経済はグローバルにつながっているが、人々の心は分断されているように思えてならない。
遠い地域で暮らす人々、さらに子や孫の世代といった未来の人々に思いをはせ、想像力を働かせる行為は、「今後どのように豊かになっていけば良いのか」を考えるきっかけになる。これまでのような金と物が中心の豊かさではなく、心をベースとした豊かさへの価値転換が求められている。
ご存じの通り、沖縄には「ゆいまーる」という言葉があり、かつては親族や集落の人々が集まり、農作業など労働交換の時にこの言葉が使われていた。今でも助け合いや、つながり、共同体といった意味合いで、沖縄の人々に受け継がれている。
沖縄では、このような人々とのつながり、そして自然や祖先とのつながりを大切にしている。この「つながり」は、自分は生かされているという価値観にも通じる重要なキーワードである。
世界で起きている愚行を少しでも減らしていくためには、自然、地域、人々がつながりを取り戻していく事が必要である。そのために、沖縄は本来持っている心をベースとした豊かさを発信する重要な役割を担っている地域である。
(鈴木修司・ゆいまーる沖縄代表取締役社長)
2017年06月11日
【No.1509】どうするのか!?琉球藍。
最近、琉球藍の生産が危機的な状況にあるという事が、沖縄の新聞で記事になっていました。

このタイミングでしっかり業界内でも琉球藍をどうしていくのかを考え、
次のアクションを起こす必要があると思います。
、、という事で、過去のブログに加筆もしながら、自分の考えも整理しておきたいと思います。
琉球藍の生産は携わる農家の方が不足している事もあって、生産が減少しています。
最近では、次の収穫を前にもうすでに在庫が無くなってしまっている状況です。
ゆいまーる沖縄のスタッフは2年前に、実際に収穫、藍製造の現場に行って、
その労働の過酷さ等を目の当たりにしました。

労働の量、大変さに対する収入の少なさ。
これは工芸業界全体の課題です。
しかも販売→製品の生産→原料の生産と川上に行けば行くほど顕著になっていきます。
それぞれの工程の状況がどうなっているのか?
これは同じ業界の人でも以外と知りません。
なので、琉球藍の出荷価格もこの20年以上大きな変化がありません。
工芸の生産者の方々も原料が高騰するのは困る。
どちらかというと、なかなか価格を上げきれなかったという状況がありました。
しかし、もうそんな事は言っていられない状況になっています。
それぞれの立場の人達が、適正な価格で仕事をしていかなければ、
工芸産業全体が崩壊していきます。
そうならないために、まずは様々な立場の人達が集い、お互いの状況を知り、理解し合う。
そのための集まりをゆいまーる沖縄 本店で昨年実施しました。
琉球藍の生産者、工芸の作り手、流通、デザイナー等様々な立場の人が集まりました。
この後、実際に琉球藍の植え付け作業を体験する企画も実施しました。

ただ、僕らの取組みだけでは、まだまだ変化を起こすには至っていません。
そんな中で、今回のように県内のメディアで大きく報じられたのは、とても良い機会だと思います。
今回の報道をきっかけに、変革の流れができてほしいと思いますし、何かしら協力ができればと考えています。
あとは、業界をどう変えていくのか。
その大きな取組みの1つは、着物業界の流通改革です。
現在の古いしがらみいっぱいの流通を変えないかぎり、作り手、そして琉球藍など原料を生産する
人々にお金がまわっていきません。
さらに、いつまでも行政の補助金がないと業界の仕組みが維持できなくなってしまいます。
琉球藍に限らず、染織業界の諸問題を根本的に解決するために、
大きな変革は待ったなしの状況です。

このタイミングでしっかり業界内でも琉球藍をどうしていくのかを考え、
次のアクションを起こす必要があると思います。
、、という事で、過去のブログに加筆もしながら、自分の考えも整理しておきたいと思います。
琉球藍の生産は携わる農家の方が不足している事もあって、生産が減少しています。
最近では、次の収穫を前にもうすでに在庫が無くなってしまっている状況です。
ゆいまーる沖縄のスタッフは2年前に、実際に収穫、藍製造の現場に行って、
その労働の過酷さ等を目の当たりにしました。

労働の量、大変さに対する収入の少なさ。
これは工芸業界全体の課題です。
しかも販売→製品の生産→原料の生産と川上に行けば行くほど顕著になっていきます。
それぞれの工程の状況がどうなっているのか?
これは同じ業界の人でも以外と知りません。
なので、琉球藍の出荷価格もこの20年以上大きな変化がありません。
工芸の生産者の方々も原料が高騰するのは困る。
どちらかというと、なかなか価格を上げきれなかったという状況がありました。
しかし、もうそんな事は言っていられない状況になっています。
それぞれの立場の人達が、適正な価格で仕事をしていかなければ、
工芸産業全体が崩壊していきます。
そうならないために、まずは様々な立場の人達が集い、お互いの状況を知り、理解し合う。
そのための集まりをゆいまーる沖縄 本店で昨年実施しました。
琉球藍の生産者、工芸の作り手、流通、デザイナー等様々な立場の人が集まりました。
この後、実際に琉球藍の植え付け作業を体験する企画も実施しました。

ただ、僕らの取組みだけでは、まだまだ変化を起こすには至っていません。
そんな中で、今回のように県内のメディアで大きく報じられたのは、とても良い機会だと思います。
今回の報道をきっかけに、変革の流れができてほしいと思いますし、何かしら協力ができればと考えています。
あとは、業界をどう変えていくのか。
その大きな取組みの1つは、着物業界の流通改革です。
現在の古いしがらみいっぱいの流通を変えないかぎり、作り手、そして琉球藍など原料を生産する
人々にお金がまわっていきません。
さらに、いつまでも行政の補助金がないと業界の仕組みが維持できなくなってしまいます。
琉球藍に限らず、染織業界の諸問題を根本的に解決するために、
大きな変革は待ったなしの状況です。
2017年05月21日
【No.1508】作り手のみなさんへ
先週は、中央会のセミナーで作り手のみなさん等へお話しをさせていただきました。
テーマは、これからの沖縄のものづくりと工房運営&チームづくりについて。

沖縄の工芸業界全体の現状、売れているのになかなか楽にはならない作り手の状況、
その中で、まずは原価計算、収益管理を工房運営にしっかり取り入れる事といった事を
お伝えさせていただきました。
(これは、沖縄県の新ニーズモデル事業で実際に使っている数値関連の資料です)

そして、今回初めてお話ししたのが、単純に「モノを作って、売る」という
これまでのモノづくりモデルからの脱却です。
特に手工芸が中心となっている沖縄のモノづくりの形態では、
モノづくりだけにとらわれていると、今の状況からなかなか抜け出せないのが現状です。
そのためにも、流通、クリエイターはもちろん、それ以外の多様な人々と連携し、
モノづくり+アルファーの付加価値の追求がこれからは必要になります。
ゆいまーる沖縄としても、今後は作り手のみなさんや、その他の人々・組織と
新たな連携、新たな価値の追求を行っていきたいと思います。
【お知らせ】ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
今年度も沖縄県の事業「沖縄県工芸製品新ニーズモデル創出事業」を
ゆいまーる沖縄が受託する事になりました。
事業の内容を簡単に言うと、工芸品の商品開発、プロモーション、販路開拓等の取組みを行います。
沖縄県内で手工芸を行っている方であれば、個人、組合等の団体どなたでも応募できます。
これまでに、たくさんの工房さんがこの事業で新たな一歩を踏み出しています。


今年度は岐阜県飛騨地方ののモノづくり、ブランドづくりの事例に関する視察、
デザイナーからの直接アドバイス、営業・PR研修、東京での展示会出展、県内での展示発表会
といったプログラムを組んでいます。
公募期間は6月12日15:00までです。
今回も離島の作り手のみなさんからもぜひご応募いただきたいので、
宮古島、石垣島でこの事業の説明会を開催します。
■宮古島
日 時:5月29日(月) 14時~16時
会 場:宮古合同庁舎2階会議室
■石垣島
日 時:5月30日(火) 10時~12時
会 場:石垣市商工会研修室(商工ホール)
応募用紙の書き方もご説明できますので、
ご不明な点がありましたら、ゆいまーる沖縄までお尋ねください。
■どんな感じで開発を行うの?過去の開発商品は?
↓ こちらをクリックしてください ↓
http://www.utaki.co.jp/newneeds/
■沖縄県のHP。こちらから事業の詳細をご覧下さい。
「平成29年度沖縄県工芸製品新ニーズモデル創出事業に係る企画提案の募集について」
↓ こちらをクリックしてください ↓
http://www.pref.okinawa.jp/site/shoko/shoko/kogei/shinni-zu/h28shinni-zuhozyo.html
ゆいまーる沖縄株式会社
担当:鈴木修司、由利玲子
〒901-2102沖縄県南風原町宮平652
TEL:098-882-6900/FAX:098-883-6996
e-mail info@utaki.cp.jp
HP http://www.utaki.co.jp/
テーマは、これからの沖縄のものづくりと工房運営&チームづくりについて。

沖縄の工芸業界全体の現状、売れているのになかなか楽にはならない作り手の状況、
その中で、まずは原価計算、収益管理を工房運営にしっかり取り入れる事といった事を
お伝えさせていただきました。
(これは、沖縄県の新ニーズモデル事業で実際に使っている数値関連の資料です)

そして、今回初めてお話ししたのが、単純に「モノを作って、売る」という
これまでのモノづくりモデルからの脱却です。
特に手工芸が中心となっている沖縄のモノづくりの形態では、
モノづくりだけにとらわれていると、今の状況からなかなか抜け出せないのが現状です。
そのためにも、流通、クリエイターはもちろん、それ以外の多様な人々と連携し、
モノづくり+アルファーの付加価値の追求がこれからは必要になります。
ゆいまーる沖縄としても、今後は作り手のみなさんや、その他の人々・組織と
新たな連携、新たな価値の追求を行っていきたいと思います。
【お知らせ】ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
今年度も沖縄県の事業「沖縄県工芸製品新ニーズモデル創出事業」を
ゆいまーる沖縄が受託する事になりました。
事業の内容を簡単に言うと、工芸品の商品開発、プロモーション、販路開拓等の取組みを行います。
沖縄県内で手工芸を行っている方であれば、個人、組合等の団体どなたでも応募できます。
これまでに、たくさんの工房さんがこの事業で新たな一歩を踏み出しています。


今年度は岐阜県飛騨地方ののモノづくり、ブランドづくりの事例に関する視察、
デザイナーからの直接アドバイス、営業・PR研修、東京での展示会出展、県内での展示発表会
といったプログラムを組んでいます。
公募期間は6月12日15:00までです。
今回も離島の作り手のみなさんからもぜひご応募いただきたいので、
宮古島、石垣島でこの事業の説明会を開催します。
■宮古島
日 時:5月29日(月) 14時~16時
会 場:宮古合同庁舎2階会議室
■石垣島
日 時:5月30日(火) 10時~12時
会 場:石垣市商工会研修室(商工ホール)
応募用紙の書き方もご説明できますので、
ご不明な点がありましたら、ゆいまーる沖縄までお尋ねください。
■どんな感じで開発を行うの?過去の開発商品は?
↓ こちらをクリックしてください ↓
http://www.utaki.co.jp/newneeds/
■沖縄県のHP。こちらから事業の詳細をご覧下さい。
「平成29年度沖縄県工芸製品新ニーズモデル創出事業に係る企画提案の募集について」
↓ こちらをクリックしてください ↓
http://www.pref.okinawa.jp/site/shoko/shoko/kogei/shinni-zu/h28shinni-zuhozyo.html
ゆいまーる沖縄株式会社
担当:鈴木修司、由利玲子
〒901-2102沖縄県南風原町宮平652
TEL:098-882-6900/FAX:098-883-6996
e-mail info@utaki.cp.jp
HP http://www.utaki.co.jp/
2017年05月13日
【No.1507】沖縄の作り手のみなさん、今年度もスタートしますよー!
今年度も沖縄県の事業「沖縄県工芸製品新ニーズモデル創出事業」を
ゆいまーる沖縄が受託する事になりました。
事業の内容を簡単に言うと、工芸品の商品開発、プロモーション、販路開拓等の取組みを行います。
沖縄県内で手工芸を行っている方であれば、個人、組合等の団体どなたでも応募できます。
特徴は何と言っても、流通を前提としたモノづくりとその仕組みの構築です。
よくあるのが、とりあえず試作品を作って展示会に出て終了。
事業が終わると活動そのものは終わり、流通につながらないというパターン。
これは、最初の設計段階で、流通を前提とせずにモノづくりをしてしまうために起こります。
流通を本業としているゆいまーる沖縄が全体のコーディネートをしますので、
どこに流通させるのかをしっかり設定した上で、原価計算、価格設定、営業方法、
工房さんが自分でできるプロモーション方法までを一緒に考えます。
これまでに、たくさんの工房さんがこの事業で新たな一歩を踏み出しています。



今年度は岐阜県飛騨地方ののモノづくり、ブランドづくりの事例に関する視察、
デザイナーからの直接アドバイス、営業・PR研修、東京での展示会出展、県内での展示発表会
といったプログラムを組んでいます。
現在は、ある意味ブームともいえる状況でよく売れている沖縄の工芸品。
しかし、売れてもなかなか作り手の収入は増えず、社会保障もありません。
そして、このブームが一段落した後、正当にモノづくりが評価される時がやって来ます。
売れている今だからこそ、長期的視点で本質的なモノづくりと
将来に希望が持てる工房運営の体質改善をしていく必要があります。
公募期間は6月12日15:00までです。
今回は離島の作り手のみなさんからもぜひご応募いただきたいので、
宮古島、石垣島でこの事業の説明会を開催します。
■宮古島
日 時:5月29日(月) 14時~16時
会 場:宮古合同庁舎2階会議室
■石垣島
日 時:5月30日(火) 10時~12時
会 場:石垣市商工会研修室(商工ホール)
応募用紙の書き方もご説明できますので、
ご不明な点がありましたら、ゆいまーる沖縄までお尋ねください。
■どんな感じで開発を行うの?過去の開発商品は?
↓ こちらをクリックしてください ↓
http://www.utaki.co.jp/newneeds/
■沖縄県のHP。こちらから事業の詳細をご覧下さい。
「平成29年度沖縄県工芸製品新ニーズモデル創出事業に係る企画提案の募集について」
↓ こちらをクリックしてください ↓
http://www.pref.okinawa.jp/site/shoko/shoko/kogei/shinni-zu/h28shinni-zuhozyo.html
ゆいまーる沖縄株式会社
担当:鈴木修司、由利玲子
〒901-2102沖縄県南風原町宮平652
TEL:098-882-6900/FAX:098-883-6996
e-mail info@utaki.cp.jp
HP http://www.utaki.co.jp/
ゆいまーる沖縄が受託する事になりました。
事業の内容を簡単に言うと、工芸品の商品開発、プロモーション、販路開拓等の取組みを行います。
沖縄県内で手工芸を行っている方であれば、個人、組合等の団体どなたでも応募できます。
特徴は何と言っても、流通を前提としたモノづくりとその仕組みの構築です。
よくあるのが、とりあえず試作品を作って展示会に出て終了。
事業が終わると活動そのものは終わり、流通につながらないというパターン。
これは、最初の設計段階で、流通を前提とせずにモノづくりをしてしまうために起こります。
流通を本業としているゆいまーる沖縄が全体のコーディネートをしますので、
どこに流通させるのかをしっかり設定した上で、原価計算、価格設定、営業方法、
工房さんが自分でできるプロモーション方法までを一緒に考えます。
これまでに、たくさんの工房さんがこの事業で新たな一歩を踏み出しています。



今年度は岐阜県飛騨地方ののモノづくり、ブランドづくりの事例に関する視察、
デザイナーからの直接アドバイス、営業・PR研修、東京での展示会出展、県内での展示発表会
といったプログラムを組んでいます。
現在は、ある意味ブームともいえる状況でよく売れている沖縄の工芸品。
しかし、売れてもなかなか作り手の収入は増えず、社会保障もありません。
そして、このブームが一段落した後、正当にモノづくりが評価される時がやって来ます。
売れている今だからこそ、長期的視点で本質的なモノづくりと
将来に希望が持てる工房運営の体質改善をしていく必要があります。
公募期間は6月12日15:00までです。
今回は離島の作り手のみなさんからもぜひご応募いただきたいので、
宮古島、石垣島でこの事業の説明会を開催します。
■宮古島
日 時:5月29日(月) 14時~16時
会 場:宮古合同庁舎2階会議室
■石垣島
日 時:5月30日(火) 10時~12時
会 場:石垣市商工会研修室(商工ホール)
応募用紙の書き方もご説明できますので、
ご不明な点がありましたら、ゆいまーる沖縄までお尋ねください。
■どんな感じで開発を行うの?過去の開発商品は?
↓ こちらをクリックしてください ↓
http://www.utaki.co.jp/newneeds/
■沖縄県のHP。こちらから事業の詳細をご覧下さい。
「平成29年度沖縄県工芸製品新ニーズモデル創出事業に係る企画提案の募集について」
↓ こちらをクリックしてください ↓
http://www.pref.okinawa.jp/site/shoko/shoko/kogei/shinni-zu/h28shinni-zuhozyo.html
ゆいまーる沖縄株式会社
担当:鈴木修司、由利玲子
〒901-2102沖縄県南風原町宮平652
TEL:098-882-6900/FAX:098-883-6996
e-mail info@utaki.cp.jp
HP http://www.utaki.co.jp/
2017年04月30日
【No.1506】ゆいまーる沖縄の早朝勉強会
先週はゆいまーる沖縄の早朝勉強会でした。
かれこれ20年近く実施している勉強会で、
始業前の6:59〜8:30まで、沖縄や仕事等をテーマにみんなで勉強します。
講師はみんなで持ち回りで行います。
今回は僕が担当という事で、「ゆいまーる沖縄の歴史と取組み」をテーマにしました。

まだ沖縄の商品が県外にほとんど流通していなかった時代、
創業者がどんな思いでこの会社を立ち上げたのか。
そして、その後のゆいまーる沖縄が歩んできた道のりを当時の写真や資料等で振り返ります。

*創業当時の通販用チラシ
今年は創業して29年目、外部環境もどんどん変化しています。
それに合わせて会社も変わります。
一昨年に引越も終わり、ゆいまーる沖縄もこれから少し大きな変化のタイミングだと
と思っています。
今回の早朝勉強会は、僕自身も、会社として変化させるコト、変化させないコト、
ここを再認識する機会でした。
最後はみんなで朝ご飯。
元スタッフの方にお願いして、毎回とっても美味しい&健康的なご飯をみんなでいただきます!

ちなみに、今回の勉強会はNHKの取材も入りました。
また放送日や内容が決まったらお知らせしますね。

かれこれ20年近く実施している勉強会で、
始業前の6:59〜8:30まで、沖縄や仕事等をテーマにみんなで勉強します。
講師はみんなで持ち回りで行います。
今回は僕が担当という事で、「ゆいまーる沖縄の歴史と取組み」をテーマにしました。

まだ沖縄の商品が県外にほとんど流通していなかった時代、
創業者がどんな思いでこの会社を立ち上げたのか。
そして、その後のゆいまーる沖縄が歩んできた道のりを当時の写真や資料等で振り返ります。

*創業当時の通販用チラシ
今年は創業して29年目、外部環境もどんどん変化しています。
それに合わせて会社も変わります。
一昨年に引越も終わり、ゆいまーる沖縄もこれから少し大きな変化のタイミングだと
と思っています。
今回の早朝勉強会は、僕自身も、会社として変化させるコト、変化させないコト、
ここを再認識する機会でした。
最後はみんなで朝ご飯。
元スタッフの方にお願いして、毎回とっても美味しい&健康的なご飯をみんなでいただきます!

ちなみに、今回の勉強会はNHKの取材も入りました。
また放送日や内容が決まったらお知らせしますね。

2017年04月28日
【No.1505】今日から「蔵出し」します!
いよいよ本日、4月28日(金)〜30日(日)まで、
ゆいまーる沖縄 本店で初開催の「蔵出し市」を開催します!
南風原町宮平にあるゆいまーる沖縄 本店。
店舗の奥には広大な!?倉庫が広がっています。

普段はほとんど値引き販売はしませんが、
生産の段階でどうしても出てしまう、ちょっとしたキズモノや布のハギレなどを
今回はじめてこの倉庫から出して、かなりお手頃な価格で販売します。
オリジナルブランド、琉球ガラス、やちむん、染織、かりゆしウェアなどなど、
うちのスタッフも欲しい!欲しい!と作業をしているショップにちょくちょく顔を出すほどの
品揃えと価格です。
ありがたい事に、開催前から結構お問い合わせをいただいております。
人気アイテムは早めに無くなってしまいますので、GWのお出かけ前にぜひお越し下さい!


ゆいまーる沖縄 本店で初開催の「蔵出し市」を開催します!
南風原町宮平にあるゆいまーる沖縄 本店。
店舗の奥には広大な!?倉庫が広がっています。

普段はほとんど値引き販売はしませんが、
生産の段階でどうしても出てしまう、ちょっとしたキズモノや布のハギレなどを
今回はじめてこの倉庫から出して、かなりお手頃な価格で販売します。
オリジナルブランド、琉球ガラス、やちむん、染織、かりゆしウェアなどなど、
うちのスタッフも欲しい!欲しい!と作業をしているショップにちょくちょく顔を出すほどの
品揃えと価格です。
ありがたい事に、開催前から結構お問い合わせをいただいております。
人気アイテムは早めに無くなってしまいますので、GWのお出かけ前にぜひお越し下さい!